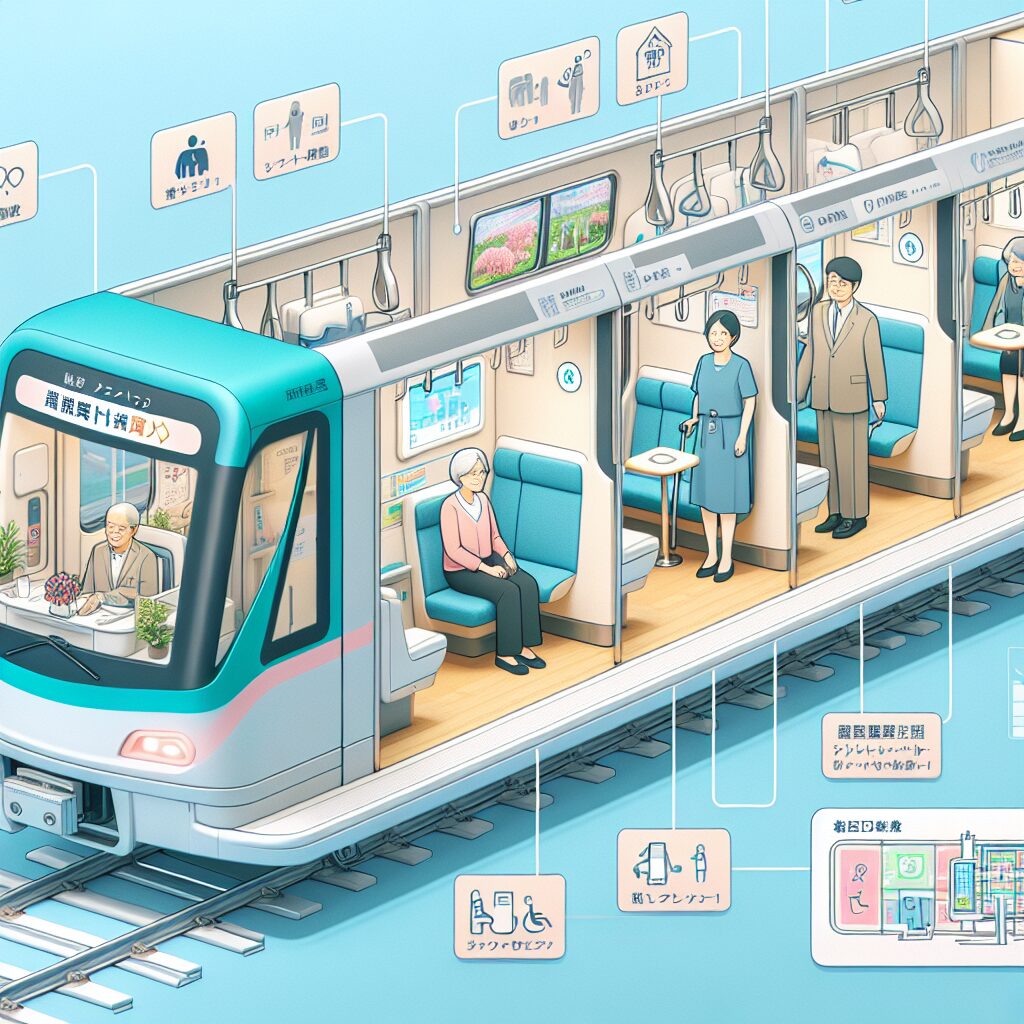
1. 名古屋鉄道が介護支援に乗り出した背景
この制度の背景には、従業員の働く環境をより良いものにし、介護に直面する社員をサポートするという明確な目的があります。
名古屋鉄道は、地元の社会福祉協議会と連携し、地域社会と共に支援を進めています。
特に、認知症支援に関する新しい取り組みも行われており、これにより地域社会全体が恩恵を受けることが期待されています。
2. 介護短日数勤務制度の具体的内容
制度の目指すところは、社員が介護を理由に離職することなく、長く働き続けられるような環境を提供することにあります。この介護短日数勤務制度は、名古屋鉄道が2023年の1月からスタートさせたものです。
社員へのアンケートによれば、同制度を活用している社員は増えており、特に50代の社員に支持されています。制度の導入前には、年20日の有給休暇を使い切ってしまい、介護離職を考える社員もいましたが、この制度の利用により、精神的・身体的な負担が軽減されています。
介護休業を取得した場合、最大1年間、月給の半分に相当する支援金が支給される仕組みがあり、介護する社員の経済的な支援も行っているのです。さらに、扶養する要介護者がいる場合には月3万円の手当も提供されるため、家計の負担が大きく減少しています。
名古屋鉄道の介護短日数勤務制度は、家庭と仕事の両立を支援する画期的な制度として評価されています。社員一人ひとりがより良いライフワークバランスを確立できるよう、今後もさらなる改善が期待されます。
3. 制度活用者の声
この制度の恩恵を受けた一人が、50代の男性社員です。
この男性は2022年末から、千葉県に住む87歳の父親の介護をすることになりました。
父親は脳梗塞の後遺症で杖を使用していましたが、新たに腸閉塞を発症し、長期入院を余儀なくされました。
退院後は要介護5の状態で、生活は車椅子によるものに変わりました。
父親の介護は母親が行っていましたが、老老介護は限界に達し、支援が必要になったのです。
男性は当初、有給休暇を利用しながら土日に父親の介護をしていましたが、有給を使い切ると体調を崩すことができない状況に陥りました。
このとき、上司から「介護短日数勤務制度」の利用を勧められました。
この制度を利用することで、彼は休職や退職を考えることなく、介護と仕事を両立することができました。
制度のおかげで、男性は安心して仕事を続けながら、現在は一人暮らしの母親のサポートも行えています。
このケースは、名古屋鉄道が導入した制度が、社員とその家族にどれほどの安心と安定をもたらしているかを物語っています。
介護支援制度は、今後も多くの社員にとって大きな支えとなるでしょう。
4. 名古屋鉄道の今後の展望
今後、名古屋鉄道はさらに支援を拡充し、社員やその家族の多様なニーズに応えることを目指しています。社員アンケートによると、約200人が同居する家族の介護を担当しており、2親等以内に要介護者がいる社員は千人に上っています。これらのデータからも分かるように、介護支援制度の重要性は一層高まっているのです。また、隠れ介護をしている社員のために、会社としてのサポート体制強化は急務といえます。
さらに、名古屋鉄道は地域や行政との連携も強化し、CSR活動の一環として地域社会への貢献にも力を入れています。鉄道事業という公共的な役割を果たしながら、地域社会の福祉に寄与することは重要であり、同社の今後の展望としても、高く評価されています。名古屋鉄道の取り組みが、他の企業のモデルとなり、業界全体の介護支援制度向上につながることが期待されます。このような取り組みを通じて、地域と共に成長し続ける企業としての地位を確立することを目指しているのです。
まとめ
この制度の導入背景には、鉄道事業に従事する社員の多くが50代であるという年齢構成が関係しています。調査によれば、少なくとも約200人の社員が同居する家族を介護しており、約1000人の社員が2親等以内の要介護者を抱えている状況です。この制度は5人の50代社員が利用していますが、それでも介護を理由に退職したケースもあり、まだまだ対策が必要です。
名鉄の介護支援制度は、同社の人事戦略担当課長の岩田氏によれば、介護休業を取得した社員に最大1年間、月給の半分に相当する支援金を支給するという新たな施策も含んでいます。このような名鉄の取り組みは、他の企業が参考にするモデルケースとし期待されており、地域や社員と共により良い社会の実現を目指しています。今後も社員と企業が共に支え合い、介護と仕事の両立を図るために、更なる制度の進化が求められます。


コメント