療育手帳の全国統一化が進行中。厚生労働省は、自治体ごとの運用の違いを解消し、知的障害者と家族の安心を図るための具体策を模索中。
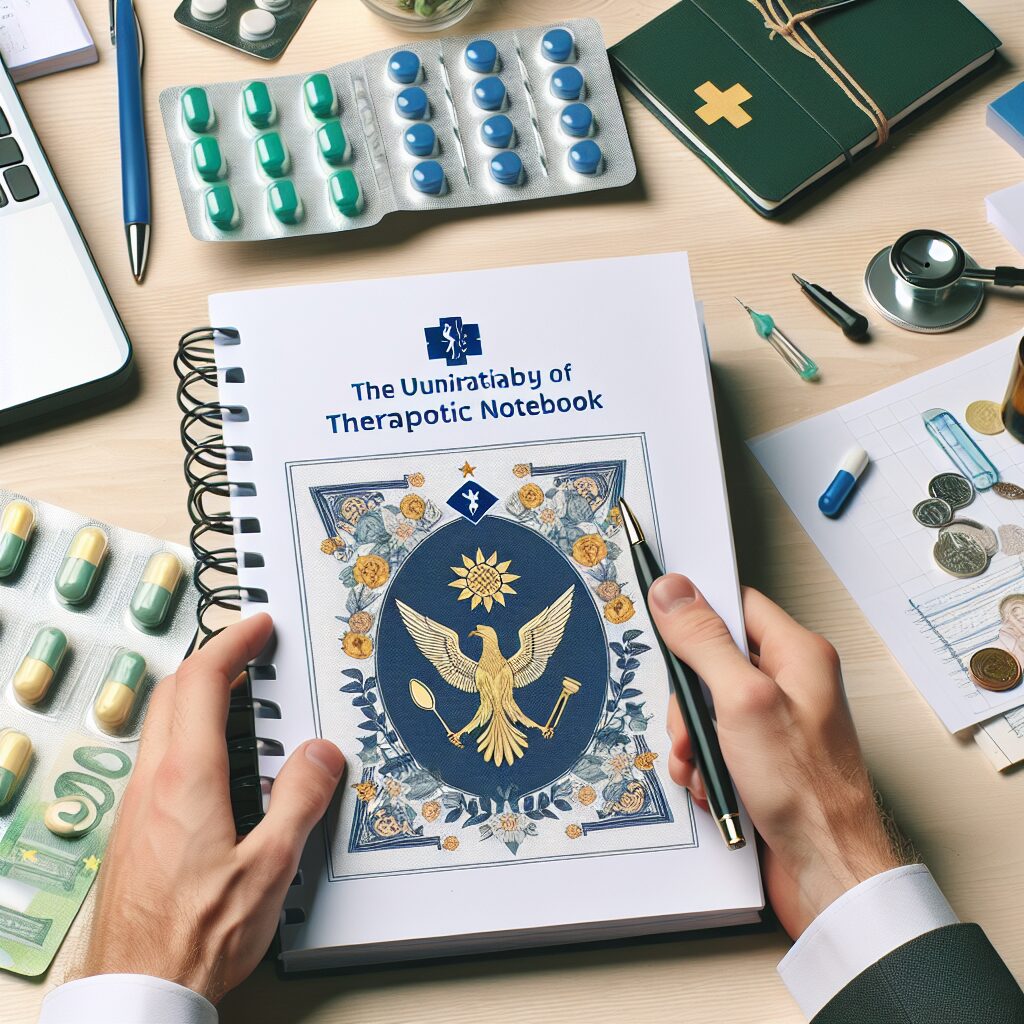
1. 療育手帳統一化の背景と狙い
療育手帳の統一化は、多くの国民にとって重要な課題として浮上しています。
この背景にあるのは、自治体ごとに運用が異なる現在の制度に起因する多くの問題です。
例えば、名称や判定基準の差異により、転居した際に以前と同じサービスが受けられなくなるリスクが指摘されています。
このような問題を解決するため、厚生労働省は介入を開始しました。
\n\n特に、転居によるサービス変更リスクを減少させることが統一化の大きな狙いです。
サービスの不安定さは、知的障害を持つ方々とその家族にとって大きな負担となっています。
例えば、ある自治体では利用できたサポートが、別の自治体では利用できない、といったケースは少なくありません。
そのため、安心して生活し続けるためには全国共通の基準が求められています。
\n\n厚生労働省は、関係者の意見を丁寧に聴取し、利益と不利益のバランスが取れた制度を目指しています。
統一化に向けた議論は活発に行われており、このプロセスでは様々な角度からの意見が集められています。
例えば、6月26日に行われた社会保障審議会障害者部会においても、意欲的な意見交換が行われ、その中で明らかにされたのは、統一化がもたらす具体的な利点と、解決すべき課題です。
\n\nこれらの動きは、2022年6月の報告書に基づいて進められており、この報告書では統一化に向けた調査研究の推進が求められました。
それに伴い、判定ガイドラインの策定と新しい評価尺度である「ABIT-CV」が開発され、26年度からはモデル自治体での試行も予定されています。
\n\n今後も、全国的に統一された判定基準が導入されることを期待しつつ、知的障害者福祉法における療育手帳の位置づけや定義の検討が進められていくでしょう。
この課題は、支援を必要とする多くの人々が安心して生活を続けるための重要な一歩となります。
この背景にあるのは、自治体ごとに運用が異なる現在の制度に起因する多くの問題です。
例えば、名称や判定基準の差異により、転居した際に以前と同じサービスが受けられなくなるリスクが指摘されています。
このような問題を解決するため、厚生労働省は介入を開始しました。
\n\n特に、転居によるサービス変更リスクを減少させることが統一化の大きな狙いです。
サービスの不安定さは、知的障害を持つ方々とその家族にとって大きな負担となっています。
例えば、ある自治体では利用できたサポートが、別の自治体では利用できない、といったケースは少なくありません。
そのため、安心して生活し続けるためには全国共通の基準が求められています。
\n\n厚生労働省は、関係者の意見を丁寧に聴取し、利益と不利益のバランスが取れた制度を目指しています。
統一化に向けた議論は活発に行われており、このプロセスでは様々な角度からの意見が集められています。
例えば、6月26日に行われた社会保障審議会障害者部会においても、意欲的な意見交換が行われ、その中で明らかにされたのは、統一化がもたらす具体的な利点と、解決すべき課題です。
\n\nこれらの動きは、2022年6月の報告書に基づいて進められており、この報告書では統一化に向けた調査研究の推進が求められました。
それに伴い、判定ガイドラインの策定と新しい評価尺度である「ABIT-CV」が開発され、26年度からはモデル自治体での試行も予定されています。
\n\n今後も、全国的に統一された判定基準が導入されることを期待しつつ、知的障害者福祉法における療育手帳の位置づけや定義の検討が進められていくでしょう。
この課題は、支援を必要とする多くの人々が安心して生活を続けるための重要な一歩となります。
2. 療育手帳の現状と課題
療育手帳は知的障害児・者にとって重要な支援の鍵ですが、現状ではいくつかの課題が指摘されています。
まず、療育手帳には法的な位置付けがなく、自治体ごとの運用に頼っているため、その名称や判定方法において一貫性が欠如しています。
これにより、判定区分が2から7と広範で、それぞれのIQの上限値や更新期間にばらつきがあり、不便さが生じているのです。
\n\n例えば、療育手帳を持つ知的障害児・者が別の自治体に転居した場合、その判定が変わってしまい、今まで受けていたサービスが途絶えてしまうという問題があります。
サービスの一貫性が確保されない限り、知的障害を持つ方々の生活の質が損なわれる可能性があるのです。
\n\n厚生労働省は、このような問題を踏まえて療育手帳の統一化を目指しています。
自治体ごとに異なる運用がもたらす不利益を防ぐために、6月26日の社会保障審議会障害者部会での議論により今後の方向性が決まりました。
\n\nまた、療育手帳の判定基準の統一は、知的障害の定義に直結するため、知的障害者福祉法における定義や位置付けを再検討する必要があります。
全国手をつなぐ育成会連合会の佐々木桃子委員も、判定基準の統一化を求めており、この方向での調査研究が進められています。
\n\nこうしたステップを踏むことで、知的障害を持つ方々の生活がより良くなり、サービスの受けやすい社会が実現できるのです。
まず、療育手帳には法的な位置付けがなく、自治体ごとの運用に頼っているため、その名称や判定方法において一貫性が欠如しています。
これにより、判定区分が2から7と広範で、それぞれのIQの上限値や更新期間にばらつきがあり、不便さが生じているのです。
\n\n例えば、療育手帳を持つ知的障害児・者が別の自治体に転居した場合、その判定が変わってしまい、今まで受けていたサービスが途絶えてしまうという問題があります。
サービスの一貫性が確保されない限り、知的障害を持つ方々の生活の質が損なわれる可能性があるのです。
\n\n厚生労働省は、このような問題を踏まえて療育手帳の統一化を目指しています。
自治体ごとに異なる運用がもたらす不利益を防ぐために、6月26日の社会保障審議会障害者部会での議論により今後の方向性が決まりました。
\n\nまた、療育手帳の判定基準の統一は、知的障害の定義に直結するため、知的障害者福祉法における定義や位置付けを再検討する必要があります。
全国手をつなぐ育成会連合会の佐々木桃子委員も、判定基準の統一化を求めており、この方向での調査研究が進められています。
\n\nこうしたステップを踏むことで、知的障害を持つ方々の生活がより良くなり、サービスの受けやすい社会が実現できるのです。
3. 統一化に向けた具体的な取り組み
厚生労働省は、知的障害児・者が持つ療育手帳の全国統一化に向けた新たな一歩を踏み出しています。
この取り組みは、療育手帳の判定基準が自治体ごとに異なるために生じる不利益を解消することを目的としています。
現在、療育手帳は法的な位置付けがないため、名称や判定方法、認定基準がバラバラであるという現状があります。
これにより、手帳を持つ知的障害児・者が自治体を越えて転居した際に、手帳の判定が変わってしまい、これまで受けられていたサービスが受けられなくなる可能性が生じています。
\n具体的な取り組みとして、厚生労働省は判定ガイドラインの策定を進めています。
また、知的機能や適応行動を評価する新たな尺度「ABIT―CV」の開発が行われ、これが療育手帳の交付判定に使用される予定です。
この尺度は、国際的な基準であるWHOの「ICD-11」(国際疾病分類第11版)に基づいており、簡便に行える検査ツールとして開発されました。
知的機能検査は127問、適応行動検査は220項目から成り立っており、2026年度にはモデル自治体での試行が予定されています。
\nさらに、全国手をつなぐ育成会連合会の関係者からは、判定基準の全国統一によって知的障害を定義づけることになり、知的障害者福祉法の中での定義や療育手帳の位置付けの検討が求められています。
このような声を受け、厚生労働省ではさらなる議論と調整を重ねながら、全国統一的な基準作りに向けた取り組みを進めています。
この取り組みは、療育手帳の判定基準が自治体ごとに異なるために生じる不利益を解消することを目的としています。
現在、療育手帳は法的な位置付けがないため、名称や判定方法、認定基準がバラバラであるという現状があります。
これにより、手帳を持つ知的障害児・者が自治体を越えて転居した際に、手帳の判定が変わってしまい、これまで受けられていたサービスが受けられなくなる可能性が生じています。
\n具体的な取り組みとして、厚生労働省は判定ガイドラインの策定を進めています。
また、知的機能や適応行動を評価する新たな尺度「ABIT―CV」の開発が行われ、これが療育手帳の交付判定に使用される予定です。
この尺度は、国際的な基準であるWHOの「ICD-11」(国際疾病分類第11版)に基づいており、簡便に行える検査ツールとして開発されました。
知的機能検査は127問、適応行動検査は220項目から成り立っており、2026年度にはモデル自治体での試行が予定されています。
\nさらに、全国手をつなぐ育成会連合会の関係者からは、判定基準の全国統一によって知的障害を定義づけることになり、知的障害者福祉法の中での定義や療育手帳の位置付けの検討が求められています。
このような声を受け、厚生労働省ではさらなる議論と調整を重ねながら、全国統一的な基準作りに向けた取り組みを進めています。
4. 全国手をつなぐ育成会連合会の要望と今後の方向性
全国手をつなぐ育成会連合会は、療育手帳の法制化を強く求めています。この背景には、全国で統一した判定基準がなければ、知的障害を持つ方々やその家族が地域によって異なる支援を受けることになり、不公平が生じるという問題があります。
実際のところ、自治体ごとに異なる基準や名称、さらには判定方法が存在しているため、転居した際には以前のサービスが受けられなくなるリスクがあるのです。この問題を解決するためには、法的な整備と、とりわけ全国的な判定基準の明確化が求められています。これまでの部会でも、こういった声が度々上がっており、佐々木桃子委員をはじめとする連合会のメンバーは、真剣にこの改革を目指しています。
また、判定基準の統一化に付随して、知的障害者福祉法における知的障害の定義そのものを見直す必要があります。なぜなら、知的障害の定義があいまいなままでは、療育手帳の法制化もその意図を十分に発揮することはできないからです。こうした背景もあり、厚生労働省の検討会の設置により、今後どのように具体的に進んでいくのかが注目されます。
統一基準の導入は、知的障害を持つ方々にとって公正で安定した支援を実現するための重要な一歩です。全国手をつなぐ育成会連合会の声に耳を傾け、多くの関係者が一丸となってこの問題を解決へと導くことが期待されています。
まとめ
厚生労働省は、知的障害児・者の生活の向上を目指し、療育手帳の全国統一化に向けた新たな一歩を踏み出しています。
現在、療育手帳は自治体ごとに運用され、名称や判定方法、認定基準が異なっているため、多くの課題が生じています。
特に他の自治体へ転居する場合、判定が変わってしまうことで、これまで受けていたサービスが受けられなくなる可能性があります。
これを解決するために、厚生労働省は検討会を設置し、関係者の意見を取り入れた議論を進めています。
\n\n2022年6月に厚生労働省の社会保障審議会障害者部会は、療育手帳の統一化に向けた調査研究を進めることを報告し、具体的な進展として、適応行動の評価尺度「ABIT-CV」を開発しました。
この評価尺度は、世界保健機関の基準を満たし、知的機能と適応行動を細かく評価できるツールです。
2026年度からは、モデル自治体での試行が予定されています。
\n\nまた、全国手をつなぐ育成会連合会からは、療育手帳の法的な位置付けや全国統一的な判定基準の導入に対する要望が出されています。
彼らは、判定基準の統一化が知的障害の定義につながることを期待しており、知的障害者福祉法における知的障害の定義や療育手帳の位置付けについても並行して検討することが望まれています。
\n\nこれらの動きは、知的障害者の支援をより充実させるために重要であり、多くの人々の注目を集めています。
療育手帳の全国統一化は、知的障害者が住む場所に関わらず、安定した支援を受けられる環境を整備するだけでなく、その家族にも安心をもたらすことが期待されます。
現在、療育手帳は自治体ごとに運用され、名称や判定方法、認定基準が異なっているため、多くの課題が生じています。
特に他の自治体へ転居する場合、判定が変わってしまうことで、これまで受けていたサービスが受けられなくなる可能性があります。
これを解決するために、厚生労働省は検討会を設置し、関係者の意見を取り入れた議論を進めています。
\n\n2022年6月に厚生労働省の社会保障審議会障害者部会は、療育手帳の統一化に向けた調査研究を進めることを報告し、具体的な進展として、適応行動の評価尺度「ABIT-CV」を開発しました。
この評価尺度は、世界保健機関の基準を満たし、知的機能と適応行動を細かく評価できるツールです。
2026年度からは、モデル自治体での試行が予定されています。
\n\nまた、全国手をつなぐ育成会連合会からは、療育手帳の法的な位置付けや全国統一的な判定基準の導入に対する要望が出されています。
彼らは、判定基準の統一化が知的障害の定義につながることを期待しており、知的障害者福祉法における知的障害の定義や療育手帳の位置付けについても並行して検討することが望まれています。
\n\nこれらの動きは、知的障害者の支援をより充実させるために重要であり、多くの人々の注目を集めています。
療育手帳の全国統一化は、知的障害者が住む場所に関わらず、安定した支援を受けられる環境を整備するだけでなく、その家族にも安心をもたらすことが期待されます。


コメント